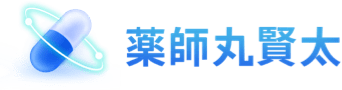導入事例
初の介護施設導入、分包業務を薬師丸賢太で効率化
― 水野介護老人保健施設でのAI-OCR導入事例 ―
これまで調剤薬局向けに展開してきたAI-OCR処方入力システム「薬師丸賢太」が、今回初めて、介護老人保健施設への導入という新たなフィールドに挑戦しました。
薬剤師の配置が手薄になりがちな介護施設では、1人の薬剤師が数百人の入居者を担当するという現場も珍しくありません。その中で、医師が発行する指示せんをもとに調剤を行い、分包機で薬をセットするという業務には、入力ミスのリスク、膨大な作業時間、人的負荷といった多くの課題が存在していました。
こうした状況を変えるべく、NeoX・タカゾノ・施設の三者で協力し、従来の業務フローを変えずに裏側の仕組みだけを刷新するという設計思想のもとで、OCR連携と分包機制御の仕組みを構築しました。
「薬局向けサービスでは通用しない」「フォーマットが定まっていない」「コード化されていない」――そんな前提の中で、AIと調剤機器との連携によって介護施設現場の業務をどこまで効率化できるのか?
そのリアルな実証結果として、今回はた水野介護老人保健施の薬局長・橋本様、そしてベンダーであるタカゾノ様に、それぞれの視点から導入プロセスと成果を伺いました。
介護施設におけるアナログ調剤という課題
現場の運用を変えず、裏側だけを刷新
AIを育てるという発想で学習精度を向上
作業時間を3分の1に、安全性も向上 ― OCR導入で現場に余裕を
三者連携で実現した現場を変えない仕組み
「この手があったか」発想の転換が連携の鍵に
連携設計のポイントは「分かりやすさ」
技術的な課題よりも、現場の使いやすさが大切
構築したノウハウは、他施設展開にも活用できる
NeoXに期待する「AIが機械を動かす未来」
介護施設におけるアナログ調剤という課題

社会医療法人社団 昭愛会
薬剤部 薬局長
橋本 和典 様
今回、薬師丸賢太を介護老人保健施設で初めて導入いただいた背景について、橋本様からお伺いできればと思います。
橋本様もともとこの施設では、薬剤師1人で、200人以上の入居者の調剤をほぼアナログで行っていました。処方せんの元となる「指示せん」はワイズマンのカルテから出るのですが、コード化されていないフリーテキストのため、分包機にデータを飛ばすことができず、すべて手入力。調剤、入力、確認、全ての業務を1人で対応するという、非常に過酷な状況でした。
さらに、入力ミスがあってはいけない、変化に気づかなくてはいけない、というミスが許されない責任による心理的な負荷も非常に大きく、「この業務を他の誰かに引き継げるだろうか?」という不安も常にありました。 それでも、非常時の医療対応や服薬管理には薬剤師の専門性が不可欠だと考え、業務委託にはせず、「ワンオペでも安全に回せる体制」を目指す中で、NeoXさんのOCR技術に出会いました。
現場の運用を変えず、裏側だけを刷新
読み取り精度に不安はありましたか?
正直ありました(笑)。ホームページも見て、導入実績も多く安心感はありましたが、どれもQRコードありの処方せんが多いようで。 当施設の「文字だけ」の指示せんがどこまで読めるのか、不安は大きかったです。
実際にサンプルをいただいてテストしたところ、想定よりも読み取り精度が高く、導入をご決断いただきました。導入にあたって特に意識されたポイントはありましたか?
最も意識したのは、「現場の運用を変えないこと」でした。 医師や看護師、他職種のスタッフが新しい操作を覚えたり、業務を変えることなく、裏側だけが刷新されている状態を実現することが前提でした。
AIを育てるという発想で学習精度を向上
導入後の使用感や、AIとの向き合い方に変化はありましたか?
最初は、今までのシステムのように「ユーザーが合わせる」前提で操作していました。でもそれだとAIは学習してくれない。 2週間ほどで「AIは子どもと一緒。ちゃんと教えて育てないといけない」ということに気づきました。 それ以降は、不具合報告も積極的に行い、正しい情報をAIに教えるという姿勢に切り替えました。
それによって、処方内容の学習精度や文脈理解も大きく向上しました。読み取った内容が正しく、分包機に自動で飛ぶようになったことで、調剤の作業時間にも変化がありましたか?
調剤作業はこれまでの3分の1に短縮されました。現在は午前中の時間だけで施設内の調剤が完了するようになり、午後には本院の業務にも対応できるほど、作業に余裕が生まれています。 これは単に作業時間が減ったというだけでなく、業務の見通しが立ち、心理的な負荷が大きく軽減されたという点でも非常に大きな成果だと感じています。

作業時間を3分の1に、安全性も向上 ― OCR導入で現場に余裕を
実際に導入してみて、どのような効果がありましたか?
まず時間が短縮されたことで、心理的な余裕が生まれました。 安全面でも、分包支援システムとの連携により、薬の組み合わせチェックなども自動で行われ、ヒューマンエラーのリスクが明らかに減りました。 それだけでなく、OCRが読み取れなかった項目は全角で表示されるよう設計してもらったので、「これは違う」と一目でわかる副次的な効果もありました。
患者さんやナースからも、「印刷された薬剤情報に刻印や注意が書いてあって助かる」といった声があり、現場全体に好影響が出ています。
三者連携で実現した現場を変えない仕組み
今回のような介護老人保健施設でのOCR連携は、薬局とは前提が異なる点が多かったと思います。タカゾノ様として、最初に橋本様から「薬師丸賢太を使えるか」というご相談を受けた際の印象や、導入に至るまでの調整についてお聞かせいただけますか?

株式会社タカゾノ
東京営業所
川村 能也 様
正直、最初は「そこまでいけるのか?」という気持ちがありました。 OCR連携といえば薬局での運用が主流で、院外処方箋を対象にしたシステムとしての印象が強かったので、指示せんのような自由記述が多い書式を本当に読み取れるのか?という不安はありました。 ただ、NeoXさんがすぐに現場を見て、実際の指示せんをサンプルとして持ち帰り、短期間で読み取りのデモを繰り返してくれたことで、「これはいける」と確信しました。
「この手があったか」発想の転換が連携の鍵に
渥美様は特に、OCRの読み取り内容をタカゾノの分包支援システムに正しく連携させる上で、工夫された点が多かったかと思います。そのあたり、技術的な観点からのご意見をお聞かせください。
院外処方箋であれば、ある程度フォーマットが決まっていて、「この位置にこの情報がある」という前提でシステム構築ができます。 でも、指示せんはそうではなく、書式がバラバラ。このフォーマットのなさが一番のハードルでした。 最初はどこまで実現可能か未知数でしたが、NeoXさんから提案いただいた構成を見て、「あ、なるほど、そういうやり方があるのか」と発想が変わった瞬間がありました。
橋本さんが掲げていた「現場の運用はそのままで、裏側だけを刷新する」という思想に合う形で、OCR→データ変換→分包システム連携という流れを作ることができました。

株式会社タカゾノ
システムソリューション部 システム1課
課長 渥美 耕太 様
連携設計のポイントは「分かりやすさ」
実際に運用が始まるまでの準備段階で、特に難しかった点や工夫された点はありますか?
医療機関において当社は部門システムとして導入しており、主体は電子カルテにあります。基幹システムである電子カルテが送ってきた内容に合わせて分包機を動かします。今回の役割としては、「分包機を動かすためにどういった形でデータを送っていただくのか?」という、どちらかというと当社の方が主体的な立場での立ち回りを求められたので、どうすれば現場で扱いやすいか?分かりやすく整理できるか?を強く意識しました。
技術的な課題よりも、現場の使いやすさが大切
連携構築時の課題という点で、技術面よりも、現場側の運用整理や交通整理に時間がかかった印象があります。その点はいかがでしたか?
まさにそうですね。技術的には想定から外れたことはほとんどなく、むしろオペレーション設計の方が大変でした。 特に初期は、「この動作は誰に聞けばいいのか?」「この不具合はどこで起きているのか?」という状況整理に時間がかかりましたが、それをマニュアル化・整理していく中でスムーズに回るようになっていきました。
構築したノウハウは、他施設展開にも活用できる
今回の取り組みで得られた知見は、今後の製品・支援体制にどう活かしていけそうですか?
今回のプロジェクトは「こうすれば介護施設でも回る」という新しいテンプレートを作れた実感があります。 調剤支援システム側での設定方法、OCRとの連携フロー、現場への説明方法など、一から構築した手順や工夫は、今後の他施設展開にもそのまま活用できると思います。
また、OCR側の精度向上を前提とした「エラー時の気づき設計」なども、薬局とは違う現場ニーズとして非常に勉強になりました。 今後も、薬局以外の現場でOCRや自動化を使っていく時に、今回の経験は大きな強みになると感じています。
NeoXに期待する「AIが機械を動かす未来」
最後に、今後のNeoXや薬師丸賢太へのご期待をお聞かせください。
国の方針として調剤の自動化が進む中で、いまはまだ「人が機械の操作を覚える」前提ですが、これからは人の言葉で機械を動かす時代が来ると思っています。 そういった制御を、AIが担えるようになることで、薬剤師がもっと対人業務に集中できる未来が実現するのではと期待しています。
現場のニーズに対して、「こうしたらどうだろう」とスピーディーに提案し、即開発できるNeoXさんの柔軟さとスピード感は本当に驚きでした。 今後も、新しい現場、新しい機能に一緒に取り組めることを楽しみにしています。
入力に追われるのではなく、患者さんの状態に目を向けられる。記憶や感覚に頼らず、誰が見ても分かる形で仕事が残せる。それは単に効率化というより、継続可能な医療体制を作るために必要な安心そのものだと実感しています。 今回の導入を通じて、NeoXさんの考え方が、まさに現場に必要な技術の在り方だと感じました。今後も、業務を支える仕組みとして、さらに多くの現場に広がっていくことを期待しています。